「最近、利用者に優しく接することができない…」「イライラが止まらなくて、もう介護を続けられないかも」
介護の現場では、心と体に大きな負担がかかる場面が少なくありません。忙しい日々や人間関係のストレス、生活の制約などが重なり、限界を感じることもあります。
あなたも、疲れているのに「頑張らなきゃ」と自分を追い込んでしまったり、周りに相談できずにひとりで抱え込んでしまった経験があるのではないでしょうか。
この記事では、そんな介護職のストレスの原因と影響を整理し、自分でできる対処法や働き方の工夫、転職や訪問介護パートの選択肢まで、具体的に解説していきます。
私も長く介護に携わってきた中で、ストレスが重なり精神を痛めてしまったこともあります。
少しでも心に余裕を持って、無理なく働くためのヒントを一緒に見つけていきましょう。
ストレスの原因は「仕事・生活・社会」が複雑に絡み合う

介護職のストレスは、決して「あなただけの問題」や「性格の弱さ」からくるものではありません。
実際には、仕事・生活・社会・周囲の空気といった複数の要因が複雑に重なり合っています。
仕事上のストレス
介護職を続けていれば、誰もが一度はこうしたストレスを経験するものです。
例えば――
- 人手不足で常に忙しい
- 夜勤やシフト制による生活リズムの乱れ
- 利用者やご家族からのクレームや理不尽な要求
- 上司や同僚との人間関係
「もっと時間をかけたいのに、次から次へと仕事が押し寄せてくる」。そんな状況では、優しく接しようと思っても難しいのは当然です。
生活上のストレス
仕事以外の生活習慣や家庭環境も大きく影響します。
- 睡眠不足や食生活の乱れ
- 家庭との両立(子育てや介護のダブルケア)
- 経済的な不安
「仕事が大変だから休みの日くらい休みたいのに、家庭の用事で休まらない」。そうやって疲れを持ち越してしまうことで、心身への負担がさらに強まります。

休みの日に体調や気分をリセットできない状況というのは、地味に効いてきます。
社会的なストレス
個人の努力だけでは解決できない、社会の構造からくるストレスもあります。
- 介護業界全体の人手不足
- 賃金や待遇の問題
- 制度の限界による現場のしわ寄せ
こうした要因は常に背景として存在しており、「どう頑張っても自分ひとりでは変えられない領域」です。
周囲から受けるストレス
ストレスは職場や家庭に限らず、社会や周囲の空気からも少なからず影響を受けます。
例えば――
- 通勤中、街でイライラした人が多くて気持ちが引きずられる
- スーパーや電車でマナーの悪さに遭遇して余裕を削られる
- ニュースやSNSのネガティブな話題で心がすり減る
介護職は「感情労働」であるため、こうした周囲の雰囲気を敏感に受け取りやすい傾向があります。

このように、ストレスの原因は仕事・生活・社会・周囲の空気と、さまざまな要素が複雑に絡み合っています。
だからこそ「イライラするのは自分が弱いから」ではなく環境や社会の影響も大きいのだと理解しておくことが大切です。
ストレスが進行するとどうなる?

介護職のストレスは、放っておくと次第に心と体に影響を及ぼします。
最初は「ちょっと疲れているだけかな」と思っていても、進行すると次のような変化が現れてきます。
身体的な症状
体は正直で、無理を続けているとすぐにサインを出します。
- 夜なかなか眠れない、眠りが浅い
- 食欲がなくなる、または過食になる
- 頭痛・肩こり・腰痛がひどくなる
- 胃腸の不調(下痢や便秘、胃の痛み)
「寝ても疲れが取れない」「お腹の調子がずっと悪い」という状態は、ストレスの蓄積を知らせる信号です。
精神的な症状
心の余裕が削られると、気持ちのコントロールが難しくなります。
- 些細なことでイライラが強くなる
- 「優しくしなきゃ」と思うほど優しくできない
- 仕事へのやる気がなくなる
- 気分が落ち込み、自己嫌悪に陥る

特に「利用者に優しくできない自分を責める」というのは、多くの介護職が経験するストレスのサインです。
行動の変化
ストレスは行動にも表れます。
- ケア中に注意力が散漫になり、ミスが増える
- 利用者や同僚に冷たく接してしまう
- 休みの日も疲れが取れず、家に引きこもりがちになる
「前はもっとできていたのに」と感じる変化があれば、ストレスの影響を疑う必要があります。
病気のリスク
こうしたサインを見逃して無理を続けると、やがて「病気」として治療が必要な段階に進行することもあります。
代表的なものは、うつ病・不安障害・自律神経失調症などです。
「ただの疲れだろう」と思って放置せず、心身に異変を感じたら早めに医療機関に相談することが大切です。

このように、ストレスを抱えたまま我慢し続けることは非常に危険です。
そして実際に、介護現場でのイライラや限界が「事件や事故」につながってしまったニュースも少なくありません。
イライラが事件や事故につながったニュースも

実際に、介護現場でのストレスが背景にあるとされる事件や事故は、ニュースでたびたび報じられています。
- 利用者への暴言・暴力に発展してしまったケース
- ケアのミスや注意不足による事故
- 職員同士のトラブルが大きくなった事例
もちろん、介護職の多くは真面目に一生懸命働いています。
しかし、心身に余裕がなくなると「いつもならできること」ができなくなり、感情を抑えきれなくなることは誰にでも起こり得ることです。
ニュースで取り上げられる事件を「ひどい人だ」と片付けるのは簡単ですが、実際には「自分も同じ状況に立たされれば…」と想像できる部分があるのではないでしょうか。
だからこそ、「イライラを限界まで我慢する」のではなく、早い段階でストレスに気づき、適切に対処することが大切なのです。

「溜め込まない」というのは本当に大事で、いい状態でいるために私も気をつけています。
介護職を辞めた理由に多いのは「人間関係」と「待遇」

介護労働安定センター「令和6年度介護労働実態調査」によれば、訪問介護員の離職率は 11.4%、介護職員全体では 12.8% でした。
これは厚生労働省「令和6年雇用動向調査」による 全産業平均 14.2% を下回っており、数字だけを見れば「介護職が特別に離職率が高い」というわけではありません。
とはいえ、毎年一定数の介護職員が辞めているのも事実です。
同調査で挙がった訪問介護の主な離職理由は次の通りでした。
- 職場の人間関係に問題があったため(21.5%)
- 他に良い仕事・職場があったため(17.2%)
- 収入が少なかったため(15.6%)
- 勤務先の事業理念や運営のあり方に不満があったため(14.9%)
数字から見えること
多くの方が「人間関係」「待遇」「職場の方針」など、環境由来のストレスを理由に辞めていることがわかります。
つまり「イライラしてしまうのは自分の性格のせい」ではなく、職場の条件や人間関係といった外部要因の影響が大きいということです。

「辞めたい」と感じるのは珍しいことではなく、むしろ同じように悩んで辞めていく人が一定数いる。
そう理解できるだけでも、「自分だけじゃない」と気持ちが少し楽になるのではないでしょうか。
ストレスにはデメリットだけでなくメリットもある
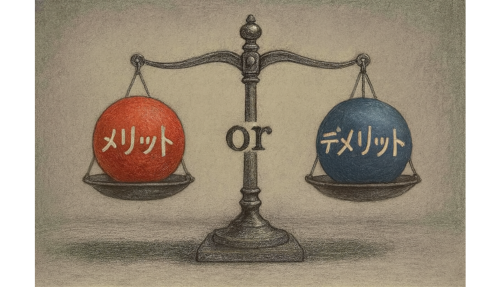
ここまで「ストレスの原因」や「悪影響」について見てきましたが、実はストレスにも 良い面と悪い面 があります。
すべてのストレスが悪いわけではなく、うまく働けば私たちにプラスになることもあるのです。
ストレスのデメリット
まずは、よく知られている悪影響です。
- 心身に疲労をため込み、不調につながる
- イライラして利用者や同僚に優しくできなくなる
- 判断力や注意力が低下し、ミスや事故につながる
介護職は「人に寄り添う仕事」だからこそ、ストレスによる余裕のなさがそのまま対人関係に表れやすいのが特徴です。
ストレスのメリット
一方で、適度なストレスは次のような良い働きをすることもあります。
- 集中力や注意力を高める
- 新しいことに挑戦する原動力になる
- 成長や学びにつながる
例えば、利用者さんの急変時に「絶対に見逃してはいけない」というプレッシャーは、むしろ集中力を高め、冷静な判断を後押しするストレスです。
良いストレスと悪いストレスの違い
大切なのは、「良いストレス」=やる気や集中力につながる負荷 と
「悪いストレス」=心身を消耗させる負荷 を見分けることです。

「疲れて倒れそうなのに、さらに夜勤が続く」ような状況は悪いストレス。
「利用者さんの笑顔のために、もうひと工夫してみよう」と思える負荷は良いストレスです。
この視点を持つことで、「ストレス=悪だからなくさなきゃ」ではなく、
「どうコントロールすればプラスにできるか」と前向きに考えられるようになります。
ストレスとの向き合い方

これまでストレスの正体や影響を見てきましたが、実際に対処していくときに大切なのは、「自分でコントロールできること」か「自分ではどうすることもできないこと」かを区別することです。
この区別ができると、「どこに力を注ぐべきか」がはっきり見えてきます。
自分でコントロールできるストレス
「自分」に関することは、基本的に自分の選択や意識次第で変えていける領域です。
- 働き方によるストレス
職種や職場は、自分で選び直すことができます。 - 人間関係における自分の関わり方
相手を変えるのは難しいですが、自分の対応や距離感は工夫できます。 - 生活習慣の乱れ
睡眠・食事・休養は、自分の意識で整えることが可能です。 - 考え方のクセ
「完璧でなければならない」という思い込みをゆるめるだけでも、ストレスは軽減します。
つまり、「自分が選択していること」は、自分で変える余地があるのです。
例えば、私もストレスが溜まってきたときは「まずしっかり眠る」ことを心がけています。
それだけでも気持ちがだいぶ楽になり、余裕が戻ってくるのを感じます。

ここは努力次第で大きく改善が期待できる部分ですよ!
自分にはどうすることもできないストレス
一方で、どんなに気を病んでも変えられないものもあります。
- 人手不足による忙しさ(業界全体の問題)
- 利用者やご家族からの理不尽な要求(相手の問題)
- 相手の性格や考え方(他人は変えられない)
- 家庭での役割(放棄できない責任)
- 介護保険制度の仕組み(社会のルール)
- 街中やSNS等のメディアからの影響(社会の空気)
これらは、自分が影響を及ぼせる範囲外のことだという認識が重要です。
私自身、相手の考えが自分と違うときに「どうにか変えよう」としてしまいがちです。
でも実際には、それができずにストレスを増やし、余計に苦しくなることがあります。
多くの介護職の方も同じ経験をしているのではないでしょうか。

この部分に力を使いすぎると消耗してしまいます。受け入れるか、距離をとるか、ですね。
介護職のストレスに対しての一般的な対処法

ストレスに押しつぶされそうなとき、まず取り入れやすいのは「セルフケア」や「考え方の工夫」です。
そして、それでも難しい場合は「職場を選び直す」「転職する」という選択肢も含めて考えることが大切です。
気持ちを切り離す練習(入り込みすぎない)
介護は「感情労働」とも呼ばれます。利用者やご家族の気持ちに寄り添うことは大切ですが、共感しすぎるとこちらが疲れ果ててしまいます。
「自分にできる範囲で寄り添う。できないことは冷静に線を引く」ことは、冷たい対応ではなく、長く働き続けるために必要なスキルです。
諦めも大事(踏み込みすぎない)
「どうしても変えられないこと」にエネルギーを注ぎ続けると、心も体も消耗してしまいます。
利用者の性格、家族の価値観、制度の仕組みなどは、自分の力では変えられない領域です。
諦めることは「投げ出すこと」ではなく、「ここは私の責任範囲ではない」と区切る賢さです。
休養・趣味・リフレッシュ
睡眠・食事・運動という基本の生活習慣は、ストレス対策の土台になります。
また、趣味や好きな時間を持つことは、心を回復させる大切なリフレッシュ手段です。
「たった30分でも自分のための時間を確保する」ことを意識すると、日々の疲れの感じ方が大きく変わります。

土台は思っているより大事です!
同僚や専門家に相談する
悩みを口に出すだけでも気持ちは軽くなります。
同僚や上司と共有することで、「自分だけが苦しんでいるわけではない」と気づけることもあります。
また、外部の相談窓口やカウンセラーを活用するのも一つの方法です。専門家に話すことで、心の整理が進みやすくなります。
転職もひとつの選択肢
どうしても改善が見込めない職場で無理を続けると、心身を壊してしまう危険があります。
ブラックな職場にしがみつくより、自分に合う環境を探すことの方が、長い目で見て自分を守ることにつながります。

がんばってるのにどうにもならないときは、環境を変えることも勇気です!
訪問介護パートは、ストレスを減らしやすい働き方

転職を検討する場合、訪問介護パートという働き方は、ストレスを回避しやすい特徴があります。
特に正社員よりも「パート勤務」の方が、その効果は大きくなります。
介護職のストレスの多くは、人間関係や働き方の制約から生まれますが、訪問介護パートであれば以下のようなメリットがあります。
- 直行直帰・単独行動が多い
職場内の人間関係によるストレスを減らし、自分のペースで仕事に集中できます。正社員と違い、会議や管理業務に追われることも少なく、心理的余裕が生まれます。 - 勤務時間や曜日を調整しやすい
家庭や副業との両立がしやすく、生活リズムに合わせた働き方が可能です。体力や時間の負担を自分でコントロールできるため、疲労が蓄積しにくくなります。 - 苦手なケアを外してもらいやすい
得意なケアに集中することで、負担を減らせます。正社員であれば責任上避けにくいケアも、パートなら柔軟に調整しやすいのが特徴です。

訪問介護パートは、一人ひとりのペースで働きやすく、無理せず続けられる環境が整いやすいですよ!
詳しいメリットについてはこちら
ストレスを減らして働くには?働き方の4つの最適化

ストレスを減らしてためには、「働き方を自分に合わせて最適化する工夫」が欠かせません。
ここでは、訪問介護パートを前提にした4つの最適化ポイントを紹介します。
① 職種の最適化:訪問介護パートに切り替える
正社員として働くと責任や業務量が増え、家庭や副業との両立も大変になります。
パート勤務を選ぶことで、メリットを最大化し、自分のペースで働きながらストレスを減らせます。
- 勤務量や責任を自分で調整できる
- 家庭や副業との両立がしやすい
- 無理なく働くことで長期的に続けやすい
- 直行直帰・単独行動が多く、職場内の人間関係ストレスを回避できる

ストレスを減らして働くなら、訪問介護パートは一つの最適解です!
② 職場の最適化:働きやすい事業所を選ぶ
職場環境は、ストレスの大きさに直結します。
自分と価値観が合う先輩や経営者がいるか、職場の雰囲気は自分に合っているかを確認することが重要です。
- 尊敬できる人がいる職場を選ぶ
- 距離を置きたい人とは無理せず適度に関わる
- 面接や見学で雰囲気を確認して自分に合う事業所を見極める
📌 自分に合う事業所を探す
👉 介護求人【ジョブメドレー】(PR)\ 希望に合う職場がきっと見つかります /
③ 現場の最適化:スムーズに仕事を進める
訪問介護では、現場での工夫次第で働きやすさが大きく変わります。
利用者の性格や希望に合わせて関わることで、日々の負担感を減らせます。
- 話を聞いて欲しい人か、自分でやりたい人か、等をよく観察する
- 利用者が大事にしていることや嫌いなことを見極める
- どうしても難しいケアは無理せず事業所に相談して外してもらう

私は「自分の意見は最小限」にして、聞き役に徹する方がスムーズだと感じています。
④ 自分の最適化:働く目的を明確にする
何のために働くのか、どこを目指すのかが明確になると、日々の負担を感じにくくなります。
目的を意識することで、多少のしんどさや困難も乗り越えやすくなります。
- 働く目的を言語化してみる
- 達成したい目標や関わり方の理想を考える
- 自分の優先順位に沿って仕事のやり方を調整する

働く目的を持つことは、日々のストレスを和らげ、長く続ける力になります
働く目的についてはこちらもご覧ください
👉訪問介護は本当にきつい? 20年続けて感じた“本当につらかったこと”
課題は収入:「訪問介護パート × 副業」という選択肢

ストレスを減らして働ける訪問介護パートですが、課題もあります。
それは 「収入の少なさ」 です。
いくら働きやすく最適化しても、生活に必要なお金が足りなければ続けていくのは難しいですよね。ここでは、介護職の収入の現実と、その課題を乗り越える方法を紹介します。
介護職の給料が低い背景
介護職の賃金が伸びにくいのは、制度の仕組みに原因があります。
介護サービスの料金(介護報酬)は国が決めているため、事業所ごとに自由に値上げできません。
その結果、利益を給与に十分反映しにくく、賃金が低めに抑えられてしまうのです。
さらに「未経験からでも始めやすい仕事」という面があり、専門性が正当に評価されにくいことも影響しています。

国の制度の中で動いている仕事だから、どうしても給料が伸びにくいんですよね。
今後の見通し
処遇改善加算などにより、少しずつ改善は進んでいます。
ただし、財政的な制約もあり、今後も 「劇的に上がる」見通しは薄い のが現実です。
収入アップの工夫
制度の枠内でも、できる工夫はあります。
- 介護福祉士など資格を取って手当を得る
- 夜勤・早朝・休日など割増賃金の時間帯を選ぶ
- 昇給制度や手当が充実している事業所に転職する
訪問介護パートの収入シミュレーションはこちら
👉どれくらい稼げる?訪問介護パートの給料・手取りを3タイプ徹底シミュレーション
「訪問介護パート × 副業」という新しい働き方
そこで注目したいのが 「パート勤務」+「副業」 の組み合わせです。
訪問介護パートは直行直帰・単独行動・短時間勤務など、働き方が柔軟なのが特徴。
この強みを活かせば、介護を続けながら副業で収入やスキルを増やすことができます。
例えば…
- 午前中に訪問介護 → 午後は在宅で副業
- 週3日は介護 → 残りを副業に充てる
ライティングやデザインなど、在宅でできるWeb系の仕事は特に相性が良く、シフトの合間でも取り組めます。

訪問介護パートの柔軟さを使えば、もう一つの収入の柱となる副業に注力していけます!
副業はすぐに大きな収入になるわけではありませんが、少しずつ積み重ねれば将来は介護以上の収入になる可能性もあります。
介護職の給料と収入アップの工夫について詳しくはこちら
👉低賃金なのはなぜ?介護職の給料安すぎる問題|収入を上げるために今やるべきこと
介護職のストレスに関するQ&A

Q1. 介護職でストレスを感じるのは自分が弱いからですか?
A. いいえ。介護職のストレスは、制度や職場環境、社会的な要因が複雑に絡んで生まれるものです。
「自分の性格のせい」と思い込む必要はまったくありません。むしろ多くの介護職員が同じ悩みを抱えています。

ストレスを感じるのは、あなたが真面目に向き合っている証拠です。
Q2. イライラが止まらないときはどうすればいいですか?
A. まずは「休む」「距離をとる」ことを優先してください。
深呼吸や短時間の散歩、誰かに気持ちを話すだけでも効果があります。
無理に我慢すると爆発につながるので、早めに小さくガス抜きをしましょう。
Q3. 職場の人間関係がつらいとき、どうすれば?
A. 自分の対応を工夫することで改善できる部分もありますが、限界があります。
「どうしても合わない」と感じるなら、転職も前向きな選択肢。
特に訪問介護パートは直行直帰・単独行動が多く、人間関係のストレスを大きく減らせます。
こちらもご覧ください
👉【訪問介護は楽しい!】20年続けて分かったやりがい・メリット・向いてる人まとめ
Q4. ストレスで体調が悪いけど病院に行くべき?
A. はい。体や心に異変を感じたら早めに受診してください。
睡眠障害や気分の落ち込みが続く場合は、うつ病などの病気につながることもあります。
「ただの疲れ」と思わず、専門家に相談することが大切です。
Q5. 給料が低くて生活が苦しいです。どうしたらいいですか?
A. 介護職は制度上、急激な賃上げは見込みにくいのが現実です。
資格取得や手当が厚い職場への転職、副業との組み合わせで収入を増やすのがおすすめです。
訪問介護パートは柔軟に働けるため、副業との両立もしやすいですよ。
Q6. 「諦める」って本当に必要?
A. はい。自分で変えられないことを抱え続けると消耗してしまいます。
「諦める=逃げ」ではなく、「手放す=賢い選択」と考えるのがおすすめです。

全部を背負う必要はありません。自分のできることに集中するのが大事ですよ!
体験談:ストレスで限界を迎えたとき

私が訪問介護事業所を立ち上げて数年が経った頃のことです。
当時は依頼が増え続け、休みもほとんど取れない状態でした。
忙しい日々ではありましたが、充実感も感じていました。
しかし、その上に予期せぬ負荷が重なりました。
従業員が担当していたご利用者のご家族から大きなクレームが入り、その対応に追われることに。
家庭では子どもが生まれ、役割が増えたうえに家庭内のトラブルも発生しました。
さらに体調不良まで重なり、不安や心配そのものが精神的なストレスとなっていきました。
そうした出来事が折り重なり、ある日「プツッ」と何かが切れたように感じました。
笑えなくなり、気力が減り、目を開けることさえ難しい。気持ちが深く沈んでいくのを自覚しました。
それでも仕事を代わってもらえる状況ではなく、なんとかやり過ごしながら業務を少しずつ減らしていきました。
同時に、意識して休む時間を確保し、回復に努めました。
精神を痛めると、回復には長い時間がかかります。人生全体が停滞してしまうこともあります。
私はこの経験から「限界を迎える前に、きちんとストレスに対処することの大切さ」を強く学びました。

今では、ストレス管理に特に注意を払うようにしています。
学び
この経験を通して痛感したのは、 「ストレスは放置すると必ず心身をむしばむ」 ということです。
仕事や家庭の責任感から無理を重ねてしまいがちですが、限界を超える前に調整することがとても大切です。
- 「これは自分でコントロールできることか?」
- 「今は休むべきタイミングではないか?」
こうした問いを意識するだけでも、心が軽くなり、状況を見直すきっかけになります。

ストレスは見えない方向からもやってきます。限界を超えてしまわないように早めに対処することが必要です!
まとめ:ストレスと上手に付き合いながら介護を続けるために

介護職はやりがいの大きな仕事ですが、その一方でストレスを抱えやすく、心身に負担をかけやすい仕事でもあります。
今回お伝えしてきたように、大切なのは 「自分の手で対処できるストレスと、どうにもできないストレスを区別する」 ことです。
そのうえで、
- セルフケアや考え方の工夫で自分を守る
- 訪問介護パートなどストレスの少ない働き方を選ぶ
- 「4つの最適化」で職場や現場を自分に合わせて整える
- 収入面は副業と組み合わせて安定させる
こうした工夫を積み重ねることで、ストレスを減らしつつ介護の仕事を長く続けることができます。

介護は“がんばりすぎない工夫”が大事。無理なく続けられる形を見つけていきましょう!
まずは自分に合う職場をチェックしてみよう
「ストレスが多い職場は避けたい」「無理なく働きたい」と感じているあなたにとって、職場選びはとても大切です。
訪問介護パートなら、直行直帰や短時間勤務など、柔軟な働き方が可能。生活リズムに合わせて、無理なく仕事を続けられます。
まずは、求人情報をチェックして自分に合う職場があるか確かめることから始めてみましょう。
\ あなたに合う働き方がきっと見つかります /

環境を変えるのは勇気がいるけど、自分を守るための大事な一歩です!



